日本の同性婚の実現は・・・
現在、世界では同性婚が認められているのは39の国・地域です。
日本では同性婚は認められていませんが、今年3月に行われた同性カップルによる「同性婚を認めないのは憲法違反だ」とする裁判の控訴審で、大阪高裁が「違憲」と判断しました。現在までに、札幌・東京・福岡・名古屋・大阪の各高裁で「違憲」との判決が相次いでいます。
また、日本国内のパートナーシップ宣誓制度を導入している自治体は、現時点で538自治体(漏れもあるかもしれませんが)となっており、日本国内の総自治体数の約3分の1にまで広がっています。
米国で同性婚が合法化されてから10年、これまでに結婚したカップルの数
アメリカでは、2015年6月26日に連邦最高裁判所が同性婚を合憲と判決し、全米で同性婚が合法化されました。
Pinknewsの記事によると、今年で米国で同性婚が認められてから10年となり、これまでに約80万組以上のカップルが結婚したそうです。記事では、同性婚をめぐる現状について以下のように紹介しています。
同性婚は経済にも影響を与え、過去10年で全米に59億ドルの経済効果と数億ドル規模の税収、雇用増をもたらした。特に南部州で結婚率の上昇が顕著だった。
一方で、31州にはいまだ同性婚を禁じる「休眠状態の法律」が残っており、最高裁判決が覆されれば多くのカップルが脆弱な立場に置かれる可能性がある。共和党の一部は判決の見直しを試みているが、バイデン政権下の2022年に成立した「結婚尊重法(Respect for Marriage Act)」が一定の保護を与えている。
しかし調査によると、同性婚カップルの約8割が「判決が覆ること」への強い不安を抱えており、すでに4分の1が法的安定性を守るための対策を講じているという」
日本の同性婚の実現はまだ先になるかもしれませんが、日本社会においても「誰もが平等に結婚できる権利」について議論がより一層深まっていくことを期待したいものです。
関連記事:Here’s how many same-sex couples have wed in US since equal marriage ruling 10 years ago



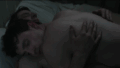

コメント